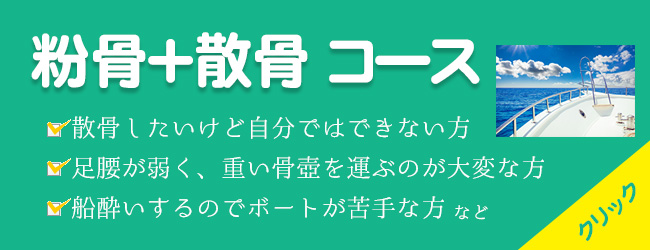葬式後の遺骨を自宅で保管するときの正しい置き方

日本国内では一部の地域を除きほとんどの場合、火葬後に遺族が遺骨を引き取ります。
引き取った遺骨はすぐにお寺の一時預かりに持って行く事もありますが、多くの場合、後飾り祭壇などを使用して自宅に安置し、一定期間供養した後、納骨したり散骨します。
遺骨の安置場所はリビング脇の和室が多い
かつて日本家屋には仏間があり、遺骨などもその部屋に安置しましたが、現在では仏間が無い家庭がほとんどなため、リビングや隣接する和室に安置している方が多いようです。
祭壇などは供花が多いので、枯れないように窓際に置きたいところですが、供物が腐敗することや、骨壺の結露を防ぐ為にも陽当たりの良い場所は避け、家の中程に配置します。
遺骨を入れた骨箱の横にお花や果物などの供物を置いておくと、風呂敷や木箱が湿気を吸い込んでカビや腐食の原因になりますので置かないようにしましょう。どうしても置きたい場合は骨箱から遠ざけて置くようにします。
遺骨を自宅で安置する方法は、主に火葬後の数日間用ですが、お盆やお彼岸でもこれらを簡素化した方法で安置する方も多いです。
以下では納骨までの正しい遺骨の安置方法を宗教別に解説したいと思います。
仏教の場合
仏教では後飾り祭壇 を使用して遺骨を安置します。自分で用意する事もできますが、葬儀とセットになっていることが多く、そちらを使用した方が安価で済むでしょう。祭壇は火葬後、葬儀社のスタッフが自宅に来てセットしてくれます。
後飾り祭壇の素材は木製や段ボール製などいろいろあり高級な漆塗りだと何十万もします。なので昔はレンタルでした。今は安価な白木製や段ボール製ですので、葬儀費用に含まれて買い取りの場合が多いです。使用後は保管しておいてお盆やお彼岸などで再利用します。
後飾り祭壇には二段式と三段式というものがあり、 葬儀の規模やお供えの多さで決まりますが、ご自宅で焼香する方も少ない現代の主流は簡素な二段式です。(コロナ後はお焼香をしないで"おり"んだけで済ます方が増えた)
遺骨や遺影などの配置方法は特に決まっていませんが、燃えやすい物は手前に置かない、遺影はなるべく正面になどの配慮は必要です。
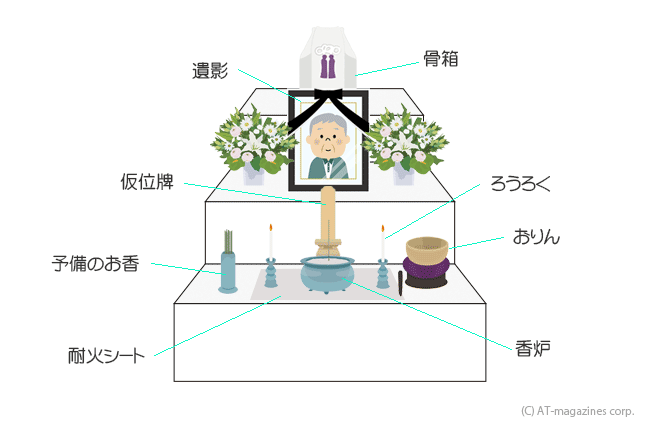
後飾り祭壇・仏式三段 配置例
【最上段】遺骨
【中段】供花 遺影 供花
【下段】予備お香 ろうそく 仮位牌(奥) 香炉(手前) ろうそく おりん
配置の際に注意すること
- 遺骨は5kg程度あり重いので端に載せないこと。骨箱が汚れないように供花や食べ物と同じ段には置かない。
- 弔問者が座った時に目線と同じか、それ以上の所に遺影を置く。
- 万が一の事を考慮し、香炉やろうそく台の下には耐火シートを敷き、燃えやすい物は周囲に置かない。(ろうそくはLED式のものが安全)
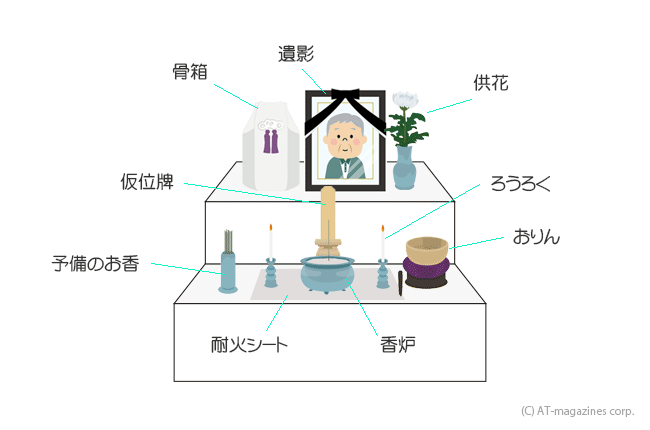
後飾り祭壇・仏式二段 配置例
【上段】遺骨 仮位牌
【下段】予備お香 香炉 (供物)
果物や鉢植え花などは重いので後飾り祭壇にはなるべく載せずに、別に手前に棚を設けるなどした方が安全面で良いです。
配置する際に注意すること
- 遺影が中央に来るように配置するが、骨箱は重いのでなるべく中央に寄せておく。(花瓶の重さで左右のバランスをとる)
- 骨箱が汚れないようにするため供花とは離す。
- 香炉やろうそくの下には万が一に備えて耐火シートを敷いておく。火事を防ぐためにろうそくはLED式が好ましい。
納骨の目安
仏教の場合、特に納骨日は決まっていませんが、火葬から四十九日以内に納骨することが最も多いようです。宗派や地域差、家庭の諸事情などもあり様々で、初七日で納骨される方もいれば納骨せずに自宅でずっと保管している方も最近では増えてきているようです。
納骨先はどこが多いの?
地方ではお墓に埋蔵する方が多いですが、都市部では墓地不足や承継者不在の問題もあってお墓は保有せず、自治体の納骨堂や永代供養に出す方が増加しています。また、最近では海洋散骨する方もとても多いです。
神道の場合
神道でも仏教と同じく 後飾り祭壇 を使用します。
自分で用意する事もできますが、葬儀とセットになっていることが多く、そちらを利用した方が安価で済みます。火葬後、葬儀社のスタッフがご自宅に来てセットしてくれます。
後飾り祭壇は木製や段ボール製などいろいろあります。高級な漆塗りだと何十万もしますが、安価な白木製や段ボール製だと数千円で購入できますので、葬儀費用に含まれて買い取りの場合が多いです。使用後は可燃ゴミとして一般家庭で処分できます。
後飾り祭壇には二段式と三段式というものがありますが、神道の場合はお供え物が多いので三段式が好ましいと思います。
配置する際に注意すること
- 神道の場合、故人は子孫を守る神として 命 になりますので、遺骨は来訪者の目線より上の最上段に祀(まつ)ります。
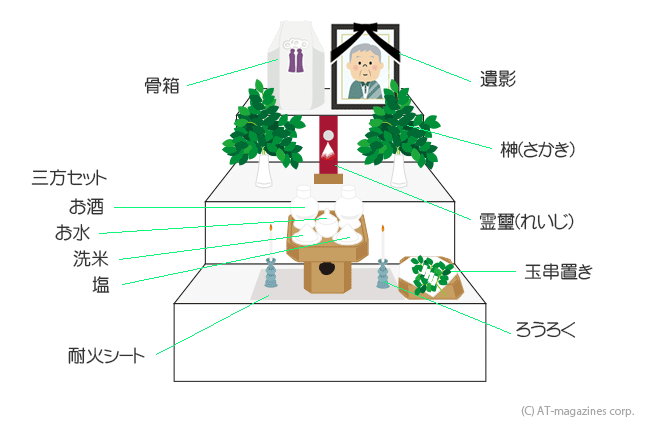
後飾り祭壇(三段式)配置例
【最上段】遺影 遺骨
【中段】
榊
霊璽
榊
【下段】
火立
三方
玉串
火立
後飾り祭壇(二段式)配置例
【上段】遺影 遺骨 霊璽
【下段奥】榊
霊璽
榊
【下段手前】火立 三方 火立
神道の場合、来訪者が来ると玉串を奉納しますので、玉串を置く台(奥行き30cm程度)を用意しておく必要があります。玉串は湿気を含んでおりますので葉汁が布に染み込まないよう玉串置きを用意しておきます。
納骨の目安
神式の場合、基本的には火葬後すぐに納骨しても良いのですが、五十日祭のタイミングで納骨することが多いです。
キリスト教の場合
キリスト教も後飾り祭壇 を使用して遺骨を安置します。自分で用意する事もできますが、葬儀とセットになっていることが多く、そちらを利用された方が安価で済みます。火葬後、葬儀社のスタッフがご自宅に来てセットしてくれます。
後飾り祭壇には二段式と三段式というものがありますが、 キリスト教の場合は祭壇の配置方法に決まりはありませんので二段式でも十分事足ります。(十字架は最上段の中央が良いとは思います)
配置の際に注意すること
- 祭壇には献花用のスペースを空けておく。葉汁が布に付かないようにトレーなどを置いておくと良いです。
- ろうそくは防火のためにLED式などがお勧めです。
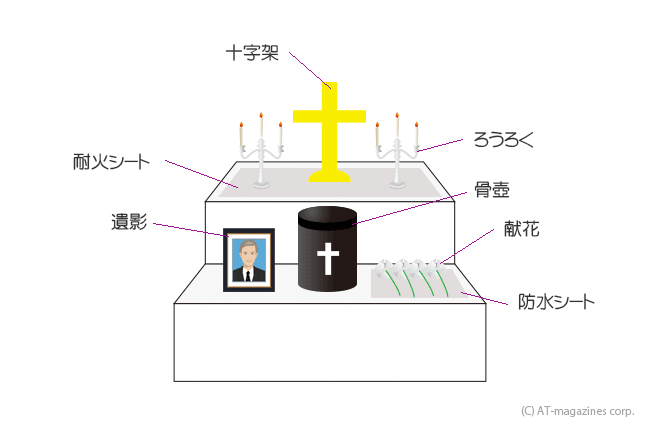
後飾り祭壇(二段式)配置例
【上段】ロウソク 十字架 ロウソク
【下段】遺影 骨壺 献花
納骨の目安
カトリックは没後30日目の「追悼ミサ」、プロテスタントは1ヶ月目の「召天記念日」がおおよその目安になります。
キリスト教の祭壇にはこんな感じのLEDキャンドルをたくさん置いてもお洒落でいいですよね。